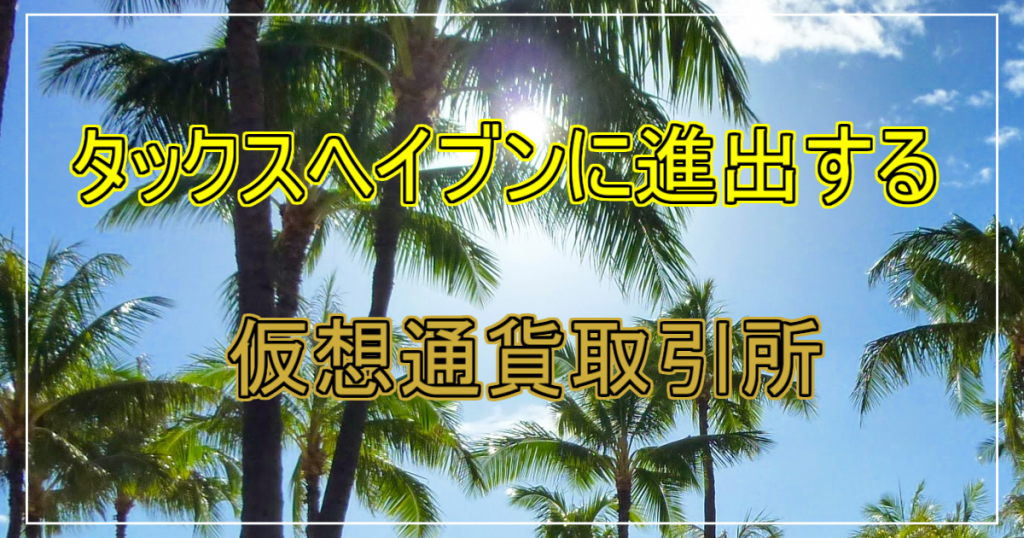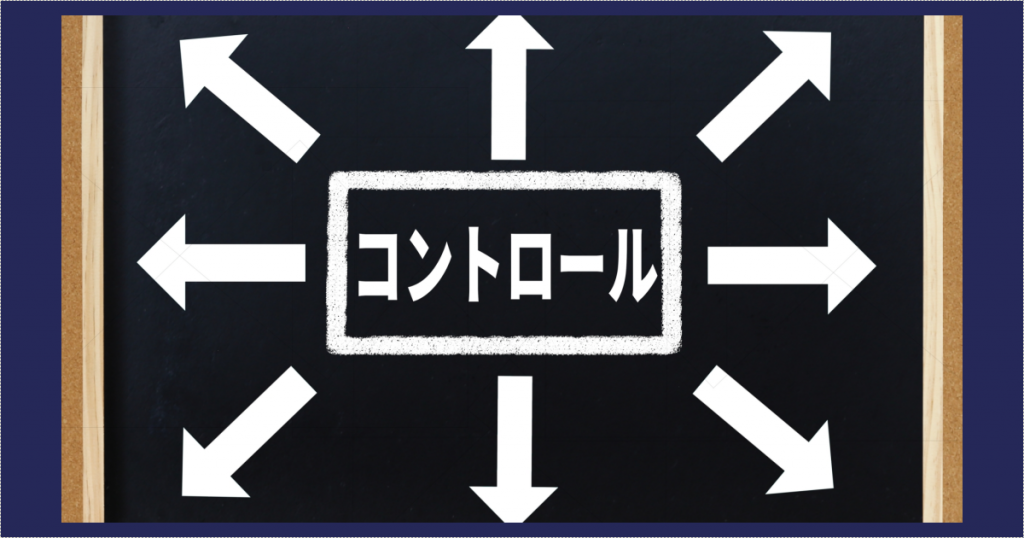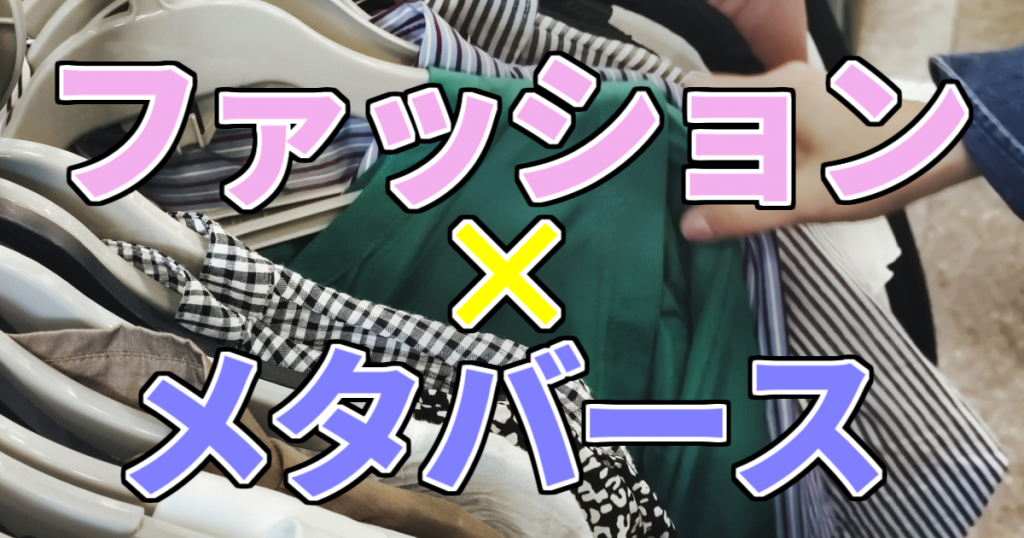※このニュースはWCL会員様向けのうち、1本分を抜粋、再編集して配信しております。
インド準備銀行、2022年度にCBDCの実証試験を開始予定=報道|2022年9月7日配信分
インド準備銀行、2022年度にCBDCの実証試験を開始予定=報道
インド準備銀行(RBI)が、2022年度内を目標に中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証試験を行う準備を進めていることがわかった。
金融系メディアMoneycontrolが5日に報じた。現在、4つの公的銀行部門(Public Sector Banks)との協議が進行しており、多数のフィンテック企業にも参加を要請しているという。
協議対象の企業には、米金融大手のフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ(FIS)も含まれる。
FISは、利子付きのCBDCやクロスボーダーCBDC決済、フラクショナルバンキングの問題などについてRISに助言を行っている形で、RBIは、CBDCについて以前から評価を行っており、2021年には、同通貨に言及したレポートを公開している。
インドは、仮想通貨関連の規制法案の整備を進めており、3月にはインド議会下院が暗号資産(仮想通貨)所得に30%の税金を課し、損益通算も認めないという法案を可決した。
本日のニュースに対する考察
支払い手段の選択肢のうちの一つとして、自身の資産をデジタル法定通貨という形で分散保有できるのならば、よりリスクを抑えるのに役立ちそうです。
また、デジタルデータを利用するということで、使い勝手も良くなります。
例えば、日本におけるSUICAのような電子マネー感覚で使えれば、非常に便利になるでしょう。
クレジットカードの様な後払いシステムだと、余計なものを買いがちですし、デビットカードだとそもそも採用している店舗が少ない(日本においては)ものです。
そもそもとして、現金を持ち歩くと、盗難のリスクを背負ってしまいます。
これが世界一安全と言われる日本国だったらわかりますが、インドなどは貧富の差が激しく、危険が伴います。
それがデータ媒体での所有であれば、なくなるリスクもぐっと下がるのではないでしょうか。
そういった意味では、中央銀行主導ということもありますから、非常に期待が持てる施策と言えますね。
ただ、筆者がこの記事の中で一番気になった部分として、一番最後の暗号通貨の所得に対する30%の税金を課すという点があります。
調べたところ、この法案は2022年4月1日より施行されていました。
これは日本の雑所得のように累進課税ではない固定値とのことで、所得の金額によっては、まだ日本の雑所得の方がましな場合があります。
日本では給与所得に加算された状態で累進課税方式になるため、330万円以上695万円以下の所得ゾーンを超えた時点で、インドの方が支払う税金が低くなります。
また、この所得ゾーンでイーブン(所得税20%+住民税10%)になりますので、日本にしろ、インドにしろ、仮想通貨にかかる税金はとてつもなく高いということが分かりますね。
ですがこれ、立場によっては、むしろもっと高い税率に設定しても良さそうです。
次の記事では、インド政府がこのような強気の税率を設定する理由の一端が見え隠れします。
どこの世界にもある所得格差ではありますが、これによれば、インドはより状況が悪化しているようですね。
どこかでこの悪化する国民の環境を改善せねばなりません。
そこで、仮想通貨で稼いだお金を富に再分配の財源とする方法。
そもそもとして、仮想通貨は明日をも生きれるかわからない人々が手を出せるような代物ではありません。
仮想通貨はそもそもとして、明日をも生きれるかわからない人々が手を出せるような代物ではありません。
参加者は、ある程度お金を持っている中流階級以上の人たちになります。
であるならば、そこで稼いだお金を民主主義の名のもとに徴収するのは正しい行いとなりますよね。
ぱっと見で言えば高そうに見える仮想通貨の税金問題ですが、格差社会、貧困問題がクローズアップされているインドという立場で見れば、それほど高すぎるというモノでもないのかもしれませんね…
おわりに
何事も実験は大切です。
試してみないとわからないことはたくさんあります。
それがやる前から無理!と言ってしまえば、科学の進歩はなかったでしょう。
我々が今ここに立って生きていられるのは、先人たちが多くの犠牲を払った結果です。
インド政府も、そうしたチャレンジを行おうとしているのですから、応援しない訳にはいきませんよね。
……手始めに、インドカレー屋さんにでも行ってみるとかどうでしょうか?
WorldCryptoLaboでは、LINEにて不定期で暗号資産関連の情報を配信しています。 無料でご登録できますので、是非お気軽にご参加ください。 登録は>>LINE登録<<からどうぞ!